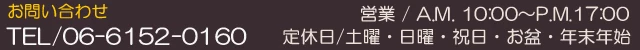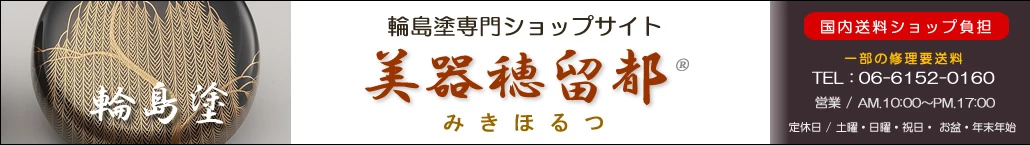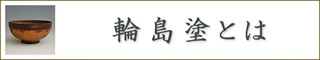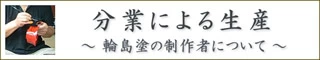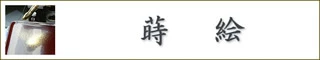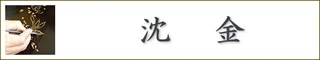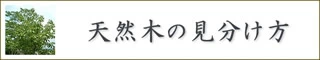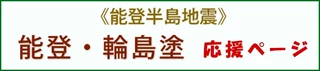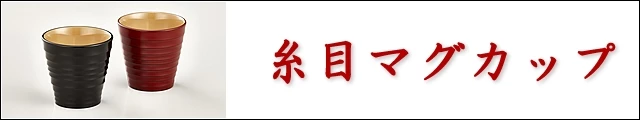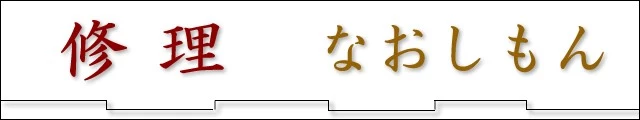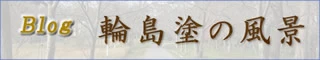漆の色について

漆の色は、うるしの樹から採取したときの樹液の色のままではありません。
うるしの樹から採取した漆(樹液)を精製し、水酸化鉄や顔料を混ぜて色を変化させて色漆(いろうるし)を作ります。
うるしの木から採取した漆(樹液)が製品の色になるまでを説明します。
うるしの樹から採取した漆(樹液)を、大まかに不純物をろ過したものが生漆(きうるし)です。
黒の漆=黒漆は、この生漆に水酸化鉄を混ぜて作ったものです。
朱や緑や白などの色漆は、精製した生漆に顔料を加えて作ります。
● 概略図~色漆が出来るまで
樹液から採取したままの漆 漆 (樹液) | ||
| ↓ | ||
| 大まかな不純物を取り除く | ||
| ↓ | ||
生漆 (きうるし) (1)接着に使われる | ||
| ↓ | ↓ | |
| 精製 | 精製の過程で鉄を混ぜて黒くする | |
| ↓ | ↓ | |
朱合漆 (しゅあいうるし) 生漆を精製したもの。飴色の半透明。 | 黒漆 (くろうるし) 昔は生漆に鉄粉を混ぜ、一晩置いて黒くし、布でこして鉄粉を捨てていました。 現在は、水酸化鉄(液体)を混ぜて作っています。 | |
| ↓ | ||
| 顔料を混ぜる | ||
| ↓ | ||
色 漆 ( いろうるし ) 半透明な朱合漆に顔料を混ぜると色漆になります。 | ||
● 主な色の種類
漆器でよく使われている主な色の種類です。
朱・本朱・洗朱・うるみ・ベンガラ・緑は、色漆によるものです。
溜塗は、塗り方によって現れる色になります。
※ ○であらわした色はあくまでイメージです。
● | 朱 (しゅ) 朱色(しゅいろ)ですが、実際には「赤」として見えます。 |
● | 本朱 (ほんしゅ) 古代朱ともいう。やや黒っぽい赤。重厚感があります。格式の高いイメージもあります。本朱の色を出すために使用されている色粉の比重が重いので、仕上がった色にどうしてもムラが出来ます。出来たムラを味わいとして楽しむ方もおられますが、気ににされる方もあります。 |
● | 洗朱 (あらいしゅ) いわゆる”朱”です。本朱から洗朱が作られます。赤みの強い朱(赤口)から、赤みの少ない淡口、黄味の強い朱(黄口≒オレンジ色、柿色)まで色の幅が広いです。本サイトでは赤みの強い朱(赤口)は「朱」としています。赤みの少ないものは「淡口」としています。 |
● | うるみ (うるみ) 朱合漆に赤口の顔料を入れたり赤口漆に黒漆を加えたもので黒味を帯びた朱色。落ち着いた雰囲気があります。 |
● | ベンガラ (べんがら) |
○ | 白 (しろ)・・・実際には白ではなくベージュ色になります。 |
● | 緑 (みどり) |
● | 溜塗(ためぬり) 溜塗の色は、色漆によるものではありません。漆の塗り方によって溜塗になります。朱漆(しゅうるし)の中塗りのあと、半透明の朱合漆(しゅあいうるし)で上塗をしたものを溜塗といいます。朱漆に朱合漆を重ねて塗ることで、朱合漆(しゅあいうるし)の上塗を透して、中塗りの朱色が透けて見え、えんじ色のように見えるようになるのが溜塗です。経年により溜塗の色は明るく変わります。 ※ 溜塗は色漆によって作られる色ではありませんが、漆器の色を区別する色ですので、色漆の種類と並べて説明しました。 |
※ 実際の漆の色は、顔料の種類や量、天候や季節などの条件により多様に変わってきます。 | |
● パール漆について
〔 パール漆について 〕 |
★ パール漆は近年石川県工業試験場が開発しました。 ★ パール漆により従来よりも鮮やかなブルーの色漆を作れるようになりました。 ★ これまで漆で作るブルーは暗く、なかなか綺麗なブルーにならなかったようです。 ★ パール調の色彩になるのでパールと言っていますが真珠は含まれていません。 ★ パール漆には光を乱反射する雲母材が用いられています。 2015年4月記す。 |
※ バール漆を使用した商品の当サイトでの掲載は現在ございません。(2019年5月 更新記載)
● いろいろな色の輪島塗
 総朱塗(そうしゅぬり)のお椀 |
 総黒塗(そうくろぬり)のお椀 |
 洗朱(あらいしゅ)のコーヒーカップ |
 四季草花の描かれた溜塗(ためぬり)の御重 |
 うるみ色のコーヒーカップ |
● 関連ブログ記事
『漆の色』 ~ Blog 輪島塗の風景~